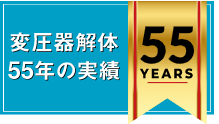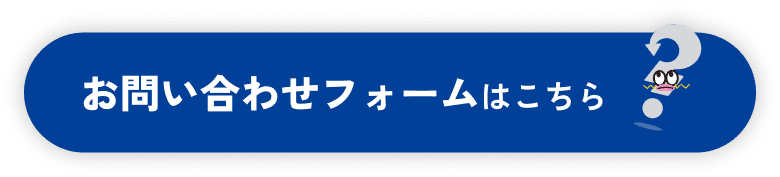Tさん「A社に産業廃棄物の依頼をしたんだ」
Dさん「A社ってあっち系の噂聞くけど、大丈夫?」
Tさん「え?何が?仮にA社が不法投棄だのやったところで、値段も格安だし、こっちはお金は払っているんだから何も心配いらないよ」
これは、とある産廃処分を依頼したTさんとその友人のDさんとの会話ですが、Tさんは、大きな環境リスクに気づいておりません。
当たり前の話になってしまうのですが、例えば、商品とは使える状態で売り物になっているわけですから、使用が困難であれば不良品として交換する権利が消費者にはありますし、ましてや、その製造工程で発生する事故などは、消費者には当然関係のないことです。
要するに、消費者は、その製品を使用できる状態で購入するし、その製造工程における事故や事件に関与する余地はありません。しかし、産業廃棄物の処理については、これとは全く違うことが言えます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)第3条第1項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」
としております。ここでいう事業者とは、お金を払う消費者(以下排出事業者)を示しますが、その次の「自らの責任において」の箇所が重要です。「自らの責任において」とは、言い換えれば、いくら産業廃棄物の業者にお金を払って任せても、処理するまでに発生した事故や事件の責任は、排出事業者にあるということです。以前の記事でも紹介させていただいておりますが、これを「排出事業者責任」と言い、産業廃棄物を発生させる事業者が、厳格に守らなければならないことなのです。例えば、前段で登場したA社が、不法投棄をして夜逃げをしたら、その原状回復にかかる費用は、全額負担することになりますし、そういう悪質産廃業者に任せたとして、インターネットに社名が公開され社会的信用を失うことになります。さらに、適正処分の根拠となるべき書類(事前調査・マニフェスト・委託契約書など)を調査され、書類への虚偽記載や記入漏れ、それを適正に処分するための再現性のない計画などが発覚すると刑事罰を受けることにもなります。排出事業者は、経済的な損害を受けるだけでなく、社会的信用を大きく毀損するリスクを背負っているのです。
では、この排出事業者責任をどのように果たせばよいのでしょう?
排出事業者責任を果たすことは、4つのフェーズから成り立ちます。第一段階では、処理業者の選定、第二段階では委託契約書の取り交わし、第三段階ではマニフェストの運用、最後に処分の確認です。
第一段階では、排出事業者責任を果たす上で、処理業者選定は最も重要です。選定方法は、以下の内容を基準にすると良いと思います。
1、処理する産廃の許可を取得しているか
2、財務諸表などから安定的な経営基盤が確立されているか
3、処分場などを訪問し、きちんと任せることができるのか
4、ISO等の環境マネジメントシステムを構築しているのか
これら1~4までを確認した上で、できればその証拠(エビデンス)を記録として残しておきましょう。訪問したなら現地の処分場の状況や許可証の標識などの写真、財務諸表等の経営情報等は、できるだけ残してファイリングしておくことをお勧めいたします。
第二段階では、産廃の契約を結びますが、排出事業者(甲)と産廃業者(乙)でお互いに押印してそれぞれ控えを5年間保管しておきましょう。また、この契約書を取り交わす前に処理業者に処理を行わせないよう十分注意してください。
これにはテンプレートがありますので、それを使用しましょう。(公益社団法人 全国産業廃棄物連合会作成の標準様式がおすすめ)
https://www.f-sanpai.com/pdf/itakukeiyajysho_01_yousiki0_all_hinagata_.pdf
盲点となりがちなのが、処理費です。処理費は事業活動を行う上で安いに越したことはありませんが、明らかに安い値段で契約したらアウトです。処理業者が不適正処理した際に、排出事業者として契約単価が安いことは罰則の対象にもなっておりますので。その地域においてだいたいの処分費を把握したうえでそれに近い値段で契約するようにしてください。
第三段階では、いよいよ処理業者が産廃の運搬を行います。ここで産廃業者の運転手とマニフェストというものを取り交わさなければなりません。マニフェストとは、産業廃棄物を処理する上で必要な運搬、処分が今どの段階にあるのかを排出事業者が監視できるようにするために開発された書類で、これをネット上で確認できる電子マニフェストと、排出事業者と処理業者と郵送でのやり取りを行う紙マニフェストがあります。個人的には電子マニフェストをお勧めしますが、その手続きを行う手間に見合った量が発生しないなどでまだまだ普及が遅れているようです。
紙マニフェストの記入用紙は全国の産業廃棄物協会で有償配布していますのでリンクを貼っておきます。
マニフェストの購入なら以下
https://www.zensanpairen.or.jp/federation/about/member/
マニフェストの運用方法
https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/
このマニフェストも記入漏れなどが、発覚すると虚偽記載として罰則の対象になりますので、上リンクの運用方法をご確認の上で間違いの無いように行わなければなりません。
最後の第四段階では、処分場で契約書通りに産業廃棄物が処分なされているのかを確認していただきたいのです。継続的に行われる場合は、毎回確認するのも大変なので、初回とせめて年に一回は現地でその確認を行う事をお勧めします。同じく証拠を残すこともお忘れなく。
排出事業者責任を全うする上で大切なことを簡単にまとめてみましたが、産業廃棄物は発生した時点で企業のリスクとなります。優良な業者を選定し、不明な点を確認し合いながら処分を進めていくことをお勧めします。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名