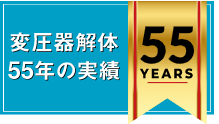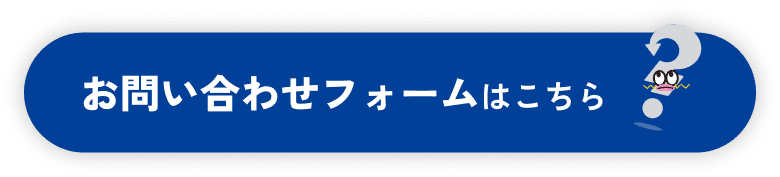コンプライアンスの関心が高まったのか、最近は廃棄物処理法の相談をいただくことが多くなりました。確かに、廃棄物の発生は企業のリスクに直結しており、それを重大と受け止めていただけるお客様が増えたことは、非常に喜ばしいことと思っています。また、そう言った相談から弊社でも把握していない案件も多々あるので、いい勉強をさせてもらっております。本記事では、相談された事例の中から2つに厳選してご紹介してみたいと思います。
下請事業者は、元請負事業者の産廃を運搬することができるのか?
先日このような質問がありました。
「下請け業者は産廃の許可なくして運搬ができるのか?」
私は、真っ先に「許可を有した下請け業者さんに運ばせてください」と正しいことをお伝えしたつもりでしたが、的を得た回答になっておらなかったので、その回答を後日改めてお伝えすることになりました。結論から申し上げますと、ある一定の条件付きで、下請業者は無許可で運搬可能です。
廃棄物の法律では、廃棄物を出した事業者が責任をもって処分しなければならないとしております。もちろん廃棄物の処理を他人に委託することもできますが、その場合は許可を有した運搬業者に運搬を、同じく許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
ところで、建築物の解体において、廃棄物を発生させた元請業者は、責任をもって処分しなければならない対象者となります。(これを排出事業者と呼んでいる)ここで元請業者は、処分場までの運搬をおこなうにあたり、以下の中から最適なものを選びます。
1、元請業者が、自ら処分場まで運ぶ
2、元請業者が、産廃の許可を有した業者に委託する
3、元請業者が、産廃の許可を有していない下請業者に運ばせる
1の元請業社が、自ら運ぶのは、問題ありませんし、2の外部に委託するのも許可さえ有していれば問題なく行うことができます。注目すべきは、3の産廃の許可を有していない下請業者に運ばせるということです。つまり、下請業者も排出事業者とみなして保管基準、処理基準を順守する位置づけにあるということです。
しかし、下請業者が、許可なく建設廃棄物を運搬できるのは、建設工事に係る請負契約書でこれを定めることが必要とされ、また以下のケースに該当する場合でないと運ぶことはできません。
1、解体工事や新築工事以外の維持修繕工事で請負代金の額が500万円以下の工事
2、引き渡された建築物の瑕疵から生じる500万円以下の補修工事
3、PCB、石綿廃棄物などの特別管理産業廃棄物は対象外
4、一回当たりの運搬される量が1立方メートル以下であるということ
元請業者さんは、常に請け負っている工事が、これらの条件に該当しているかを確認していただき、適正な処理方法を選定していただけたらと思います。
排出事業者は、無許可で積替え保管を行っていいのか?
発生した産業廃棄物は、許可を持っていなくても元請業者であれば、自ら処分場に運んでも問題はございません。(ただし、保管基準、運搬基準は満たす必要がある)
産業廃棄物の法律(廃掃法)では、自社の工事等で発生した産業廃棄物は、自ら行う運搬であれば許可が不要で、処分場まで持ち込むことができます。しかし大きい解体工事現場などでは、自社でトラックを所有していないケースもあるので、産業廃棄物について収集運搬の許可を有した業者に委託するケースが多く見受けられます。
あるリフォーム会社さんが、現場に赴き、窓の修繕工事などを行っていた時のことです。
その際、壊れた窓と窓枠は丸ごと取り替え交換することになるので、不要となったそれらは、産業廃棄物として処分することとなります。そのリフォーム会社さんは、産業廃棄物を排出場所である現場から自社運搬で、産業廃棄物処理場に持っていくことにしておりました。
ここまでは、排出事業者が自ら処分場に運搬する行為なので、無許可であっても問題ありません。
問題は、徐々にこれら産廃物を自社の倉庫に一旦集積し、一定量になってから産廃業者さんに委託するようになっていたのです。
これについてわたくしは、「御社の工事によって発生する産廃であれば、自社運搬で直接処分場に持ち込むことは可能ですが、産廃を一時保管するのは、違法なのでやめた方が良いですよ」と伝えました。しかしこれは的を得た提案になっておりませんでした。
排出事業者の積替え保管
産業廃棄物の許可業者が、産業廃棄物を直接処分場に持ち込まず、一旦置き場などに集積し、まとめてから処分場に持ち込むやり方を「積替え保管」といいます。このようなやり方をするには、「産業廃棄物収集運搬(積替え保管)」としての許可を取得しなければなりません。今回のケースでは、リフォーム会社さんが、自社の工事で発生した産廃を直接処分場に持ち込まず、一旦自社工場に集積させるということでした。自社運搬の場合は、産業廃棄物の許可が不要ですが、積替え保管を行うとなると話が違います。このケースはでは、廃掃法施行規則第 8 条の 2 の 2(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)に当てはまります。

当該保管の用に供される場所の面積が 300 ㎡以上である場所において行われる保管であって、次のいずれにも該当しないもの。(施行規則第 8 条の 2 の 2)
1 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
2 法第 15 条第 1 項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)の適正な処理の推進に関する特別措置法第 8 条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
つまり、排出事業者(元請事業者)は、建設廃棄物を現場外で保管する場合は、廃棄物を種類ごとに分けて保管し、300㎡以上の場所で保管する際は、都道府県知事に届け出なければならないということです。ただしPCB廃棄物は、これらの保管場所を都道府県知事が既に把握していることから、届出の対象外にしております。
これは、少量の産廃が発生する工事業者にとって朗報です。
積替え保管を行うにはどのような案件でも積替え保管の許可を取得しなければならないと思われがちなのですが、排出事業者に限っては、一定量までであれば、現場以外での保管も届出無しで可能ということになるからです。しかし、きちんと分別して飛散しないようにするとか、積み上げの高さを順守するといった保管基準は守らなければなりません。
廃掃法は、あくまでも私たちの生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図ることを目的としております。このような法律の趣旨を踏まえた上で、どのようにしたら効率的に産業廃棄物を適正に処分していけるかを総合的に考えて答えを導き出していかなくてはなりません。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名