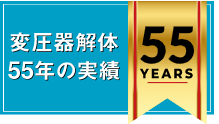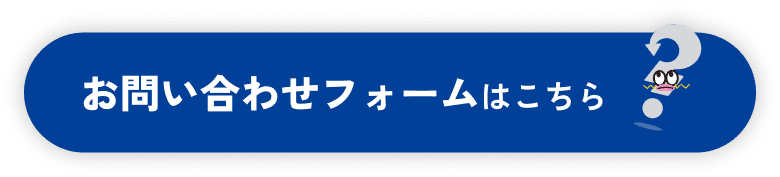1968年に起きたカネミ油症事件がPCBによる有害性が世間を震撼させてから、PCBに代替する商品を使用するまで時間はかかりませんでした。PCBの分子構造のよく似た「ジフェニール」を熱媒体で使用する企業が出てきたのです。近年PCBは、「ポリ塩化ビフェニル」という名称が一般的ですが、1970年代はじめころは「ポリ塩化ジフェニール」とも呼称されておりました。要するにPCBの分子構造を若干変化させた化学物質が「ジフェニール」というわけです。
そして事件は起こります。
1973年4月、千葉ニッコー株式会社(親会社は、日本興油株式会社)で熱媒体と使用していた「ジフェニール」が食用油に混入していたのです。当時同社から食用油を大量に仕入れ、マヨネーズなどの原料にしていた〇ュー〇ーマヨネーズ株式会社が自主回収を始めたおかげもあって、カネミ油症事件のような大きな被害でこそなりませんでしたが、わずか5年前に起きたカネミ油症事件の教訓が全く活かされていないことを象徴する出来事であったのです。(ニッコー事件)
愚かにも同じことを繰り返してしまったのです。
原因は、PCBなどの化学物質の恐ろしさなどが、世間を騒ぎ立てることで、本質的な問題解決に至らないという事です。本質的な問題とは、私たちが化学物質に頼らなければ今のような快適な生活を享受することができないことを理解したうえで、どのように有害な化学物質を管理していくかということです。ニッコー事件は、安全性を証明せずに、PCBの分子構造を多少変更して「ジフェニール」を生み出し、カネミ油症事件と同じようにずさんな管理によって食品に化学物質を混入させてしまった事件です。同社は、世間が化学物質の恐怖に怯えるほど、その化学物質の根絶だけが先行し、代替品の安全性の不明確性や、ずさんな管理の死角を逆手にとったのです。
これらを鑑みてようやく政府は、ニッコー事件同年の1973年5月に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律「化審法」の国会審議を通過させます。要は、企業が新しい化学物質を製造するには、審査を受ける義務があるという法律です。逆に言うといままでにこういう化学物質の法律が、無かったというのが恐ろしいと感じます。
ちなみに「化審法」は、大きく分けて次の三つの部分から構成されています。
1、新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度
2、製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価
3、性状に応じて「第一種特定化学物質」等に指定し、製造・輸入数量の把握、有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限等
経済産業省HPより引用
この「化審法」という法律のおかげで、私たちは、化学物質を安全に管理した上で、快適な生活を得られるようになったのです。社会の問題解決のために作られる法律は、知らないところで私たちの快適で安全な生活を支えているのです。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名