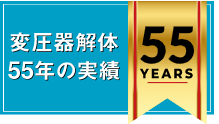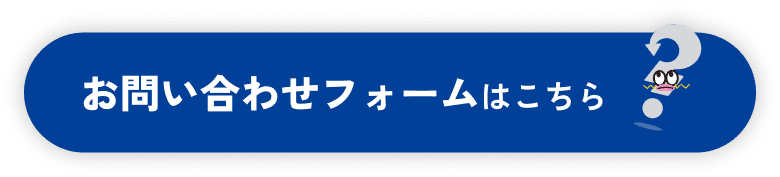20世紀に発明され、使用されてきたDDT、PCBなどの人体に有害な化学物質は、一刻も早く根絶しなければなりませんが、とかくそれだけを目的にしてしまうと本質的なことを見失うかもしれません。本記事では、化学物質と環境の共存について触れてみたいと思います。
私たちの今ある生活は、全てが快適です。
暗ければ電気を付ければ良いし、寒ければ暖房もある。食べるものも困りませんし、行きたいところがあればだいたいどこにでも行けます。これらの快適さは、化学物質を含めた科学の発展によってもたらされたものであり、今更、化学物質を否定することができないのは、周知の事実であります。
こんな話があります。
アメリカで始めてPCBの工業化を進めたモンサント社においては、PCBの有害性が全米で世論が騒ぎ出す頃の1968年頃から自主回収を始めます。同社は、例えば、耐熱用タイル、ゴム、ノンカーボン紙などの直接PCBが外部と接触する製品への販売を禁止、回収を行い、変圧器やコンデンサに使用する絶縁油用PCBなどが密閉された製品への販路だけは残そうとしました。会社経営を行う上で、実に合理性があって、素晴らしき英断であったと思います。つまり電気の絶縁性や不燃性を考えれば、PCBほど素晴らしい物質はありません。変圧器やコンデンサの火事が防止できたことで、多くの犠牲者を出さなくとも済んだかもしれませんし、現にそれによって交通網も大きく発展してまいりました。
「PCB=悪」ではなかったのです。
問題なのは、PCBを含む化学物質の特性を理解せぬまま製造、使用し河川や海を汚染させ食品公害を招いたことが原因だったのです。それを象徴したのが、日本で起きた「カネミ油症事件」でした。カネミ倉庫とその関係者は、熱媒体用に使用していたPCBの加熱パイプや各種バルブの点検を怠っていただけでなく、被害者に対する誠実さに大きく欠けておりました。しかし世論は、カネミ倉庫の企業体質にクローズアップせずに、単にPCBという化学物質を「危険化学物質」として取り上げることに注力しました。
本事件は、単なる「人災」だったことにもっと目を向けるべきです。

化学物質は、工業用のみならず、医療用の薬などでも開発を進めていかなければなりませんし、前段でも記述したように、私たちが豊かに生活できるのも化学物質による恩恵が大きいのです。そのように考えますと、私たちにとって化学物質の発展は重要なことであり、守っていかなければなりません。しかしその管理を怠ってしまえば途端に環境や人体を汚染し、取り返しのつかないことになるのです。カネミ油症事件は、化学物質の大切さと管理の重要さ2つを併せ持つ事件であったのかもしれません。化学物質の特性を十分理解し、管理を徹底させていくことが、人をより豊かにし、環境を守っていくことにつながっていくのです。