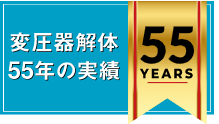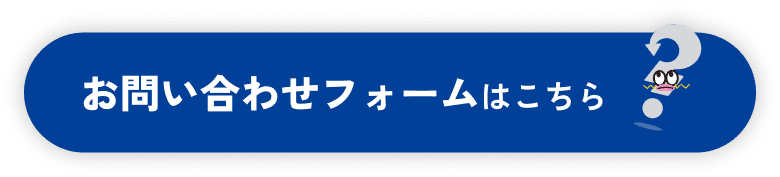「作物が枯れたのもこの2.4Dを含んだ灌漑を受けたせいだが、この2.4Dは、様々な化学物質が水や光に触れて新しい化合物を自動的に作り出している」
沈黙の春「レイチェルカーソン」より抜粋
この文節からは、化学物質が環境に放出された時に起こる化学反応の恐ろしさをうかがい知ることができます。他にも化学反応を起こす例は、たくさんありますが、PCBも例外ではありません。
PCBの性質と化学反応
実は、カネミ倉庫の熱媒体で使用していたPCBは、熱することでそれよりも何百倍もの毒性のある化学物質に変化していたということも言われております。
PCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)という化学物質です。
ただでさえ有害なPCBの数百倍もの有毒性のある化学物質に変化したのです。カネミ油症事件はPCBによって引き起こされた食品公害と言われておりますが、実質的にはこのPCDFによって引き起こされたものかもしれません。
無火気工法による変圧器の切断作業
以前のブログでもお伝えしておりますが、変圧器の切断は無火気で行うことが既に常識となっております。
ところで、なぜ無火気で切断しなければならないのでしょう。一般的な理由は2つあると言われております。1つ目は、火事が発生してしまうと鎮火が困難であるという事と、二つ目は、PCB油を燃焼させることで、PCBが大気中に放出されるばかりか、作業員がそのPCBを吸引するリスクが高まるからです。
ライフラインに火事が起きると多大な損害が発生する
切断解体を要する大型変圧器が設置されている場所は、電気というインフラを担っている変電所であるケースがほとんどです。火事を起こして1万世帯以上に対し、影響が出る可能性があるので、慎重にならざるを得ません。
実際、PCBは燃えにくいという性質から火事は起こしにくいのですが、燃え出した炎と変圧器の内部にあるベークライトや紙との相性の良さから、さらに火炎が強くなり、鎮火困難となります。そのリスクを考えて、無火気工法を採用するのです。
PCB油を燃焼させることで、PCBが大気中に放出される?
果たして燃焼させたPCBはそのままPCBとして環境中に放出されるのでしょうか?燃焼させることで、前段で解説したさらに有害なPCDFに姿を変えている可能性があるのはないでしょうか?要するに、カネミ油症事件の熱媒体PCBからPCDFが検出されているのは、熱を加えたことが要因だったので、燃焼させることで化学変化を起こすのは、当然あり得ることなのです。しかし一方で、無害になるという考え方もあります。環境省の低濃度PCB無害化処理施設の基準「低濃度 PCB 廃棄物の焼却処理の燃焼温度の基準について」によれば、一般に燃焼条件を「850℃以上で2秒以上滞留」と記されており、ガウジングやガス溶断工法などの火気で行う場合の鉄を切断する際の燃焼温度は、発火温度が900度に達するので、化学物質が消滅する(無害化される)基準をクリアする理屈となります。

このように考えていきますと、化学物質の化学反応と無害化は、実に紙一重であることがお分かりになるかと思います。また、地下水などに未だに眠っている化学物質が、光や水、放射能と結びつくことでどのような有害物質が発生するかも想定できませんし、野菜の種類によって使用されている農薬が違えば、調理の際、化学反応を引き起こすことだってありえます。未だに解明されていない化学反応は、どのような弊害を私たちにもたらすのでしょう。普段私たちが食べている物、使用している物に含有された化学物質を正しく理解していくことが強く求められるのではないでしょうか。