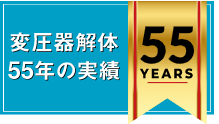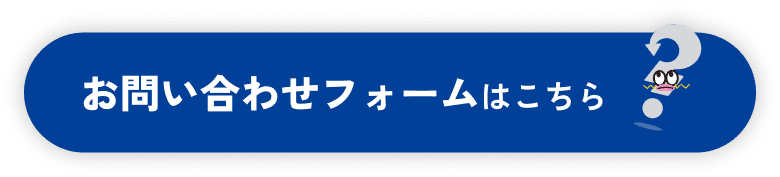前回までは、日本のPCBの処理にようやく光が差し込むところまで、解説させていただきましたが、本記事からは、光が差し込んで、いよいよその光に向かっていく様を解説させていただきたいと思います。
ストックホルム条約とは?
ストックホルム条約(POPs条約)とは、 DDTやPCBなどの化学物質について、加盟国の使用に関する条約で、要するに化学物質をこれ以上環境中に放出すると人類の存続に関わってくるので、各国力を合わせて、これらの製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減をしていきましょうという約束事を決定したということです。
ストックホルム条約参加加盟国は、以下リンクより↓↓↓
http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx
ストックホルム条約が、2001年に採択され、2004年に発効します。採択とは、各国から出た案などを、まとめて決定するにとどまることを示し、発効とは国際的な法律として条約が効果をもつことを意味します。ちなみに、ストックホルム条約は定期的に締約国会議(COP)を開催して常に最新化を図っており、今年は、2019年4月にジュネーブ(スイス)において、第9回締約国会議(COP9)が開催され、新たに化学物質を2点追加することが決定されました。

少し話をまとめますと。1964年に発生した油症事件によって、PCBが大きな社会問題となり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により製造・輸入・使用が禁止されましたが、処理施設の整備が進まなかったことから、約30年近く保管が続いておりました。ところが、1991年の「廃棄物処理法(廃掃法)」で、PCBを「特別管理産業廃棄物」として厳格な管理が求められ、さらに日本は、ストックホルム条約が2001年に採択されたこの条約を受けて、PCB特別措置法(PCB特措法)を制定します。この制定により、日本で始めて処理期限が明確になったのです。当時定められた時の処理期限は、平成28年まででした。(現在では延長となって令和9年までとしている)このように徐々にPCBの無害化が再現性の高いものとなっていくのです。
PCBの発見と撤廃の運命
個人的に、DDTやPCBなどの条約が、スウェーデンの首都ストックホルムで開催されたことは、ある因縁が隠れているように思っています。「シリーズ2」でも触れておりますが、実は、遡ること1960年初めころは、魚や鳥などの汚染がDDTであることが、発見できていたもののPCBが汚染源であることは、分かっておりませんでした。そして1966年にストックホルム大学がオジロワシ体内中に世界で始めてPCBを確認するのです。「世界で始めてPCBが確認できたのがストックホルムで、その後始末もストックホルム」というところが運命的に感じてしまうわけです。どのような意図で、このストックホルムという地で、化学物質の廃絶の会議を行ったかは分かりませんが、おそらくこのような運命的な意図もあるのではないかと思ってしまいます。
いよいよPCB廃棄物もこの運命の条約を機に、終盤戦にさしかかろうとしていますが、未だに不明機器が存在していることも言われております。特措法によってPCBを処分しなければならないという考え方も大切ですが、世界一汚染された日本についての危機感を皆さまと共有させていただき、化学物質の汚染の問題解決に向かっていければと思います。
参考文献:沈黙の春(レイチェルカーソン著):化学物質と人間(磯野直秀著):複合汚染(有吉佐和子著)
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名