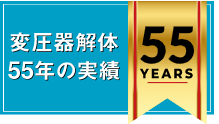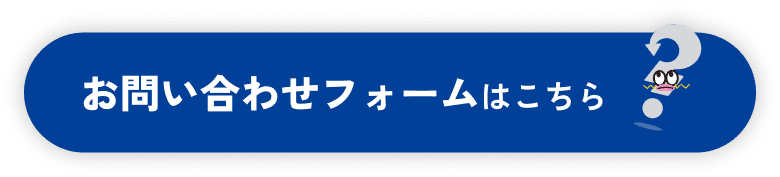地下水、河川や田畑、上下水道にPCB油が入り混じると甚大な環境問題へと発展する可能性があるため、綿密な環境分析調査を行う必要があり、環境基準を超えていれば掘削などを実施し、汚染物を除去しなければなりません。
PCB油を漏洩させた場合の原状回復に伴う費用は、3億くらいを想定しておく必要があると言われておりますが、皆様が保管しているPCB汚染物は、漏洩しないような対策を行っているでしょうか?本記事では、この漏洩防止対策について考えてみたいと思います。
PCBの保管中の漏洩事故が最も恐ろしい

弊社では、PCB油の変圧器の抜油や解体から、収集運搬までの一連の工程の中で起きた漏洩事故について、3億円を限度に補償を受けることができる損害賠償責任保険に加入しております。特に、田畑や用水路などに囲まれた変電所等のPCBの撤去作業は、漏洩すれば田畑や用水路に混入するリスクが想定できますので、運搬中に発生した事故のみならず、撤去作業中にも起きた汚染も補償されるのは、非常に安心です。また、作業中に発生したPCBの漏洩は即対応できるので、漏洩を想定した教育訓練やそれに伴う道具を準備していれば大きな汚染にはつながりにくいかと思います。一方で懸念されるのが、変電所等にPCB汚染物が保管されているケースです。管理の行き届いていない無人の変電所等では、PCBの漏洩事故が発生しても誰も発見できず、PCB油が垂れ流しになる可能性があるのです。また損害賠償責任保険に加入していないケースも多いので、環境汚染が発生した時の対応の出口が見えないのです。
PCBの漏洩防止には、処分・抜油・補助容器で対応する。
では、なぜ鉄の容器(変圧器・コンデンサやドラム缶)に入ったPCB油が漏洩してしまうのでしょう。原因は大きく2つあります。
1つ目は、容器の経年劣化によって生じた錆びから穴が開き漏洩するケースです。2つ目は高温によるPCB油の膨張によって引き起こされる容器の破損です。夏場における高温による油の膨張の圧力は、変圧器の鉄と鉄の溶接目やブッシング部を突き破るほどです。
これらの対策でお勧めするのが、抜油(液抜きとも言っています)を行うか、その容器のPCB油が全部流れ出ても、それが収まる能力を有する補助容器に入れることです。既に経年劣化等で錆びて穴が開いている場合は、どちらも併用して行うことが求められます。
早期処分をご検討ください。
これらPCBの漏洩防止対策が、汚染などを防ぐ有効な手段となりますが、さらに良いのは早めの処分です。PCB汚染物を抱えること自体が、土壌や地下汚染を招くリスクになるだけだく、盗難や紛失のリスクにも直結してまいります。高濃度PCBの処分場は令和3年には概ね閉鎖になりますし、低濃度PCBも令和9年までの処分期限があることから、処分が遅れると混雑、順番待ちなどが発生し、期限内処分に間に合わなくなる可能性も出てくるかもしれません。もちろん、今年度中の予算が立たないとか、タックスコントロールになどで決算前でないとPCB処分の稟議が下りないとか、それぞれPCB所有者様の事情もあるかと思います。しかし期限ギリギリまで所有することのリスクと、それにかかる経費も加味すれば早期処分の方が、お得なこともあるかもしれませんので是非ご検討ください。
いかがでしたでしょう。PCBの漏洩事故は、重大な環境汚染を引き起こす可能性があります。これらを防ぐには、やはりPCB廃棄物の保管管理を徹底することと早期処分があげられます。もう一度御社のPCB廃棄物について漏洩などの保管状況を確認して、お近くのPCB処理業者に相談してみてはいかがでしょう。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名